子供が小学生になっても時短勤務を続けられる?小学校卒業まで時短できる会社もある

子どもが成長し学校に通うようになると、親の生活や仕事のリズムまで大きく変わります。宿題や翌日の準備などサポートが必要な年齢だからこそ、親もまだまだ時短勤務を続けたいと感じることもあるでしょう。しかし、時短勤務をいつまで認めるかは企業による差が大きく、どの会社にいるか次第で「小1の壁」の突破しやすさも変わるので注意が必要です。
本記事では、子どもが何歳になるまで時短勤務を続けられるか解説します。なかには小学校卒業まで時短できる会社もあるので、チェックしてみましょう。
もくじ
子供が小学生になっても時短勤務が必要な理由

まずは、子供が小学生になっても時短勤務が必要な理由を解説します。子どもが小学生になるとある程度手が離れそうなイメージがありますが、なぜ時短勤務を希望するワーママが多いのか、理由を探ってみましょう。
保育園より小学校・学童の方が預かり時間が短いから
保育園より小学校・学童の方が預かり時間が短いため、「子どもが早く帰宅してしまう(=親も早く帰らなくてはいけない)」という問題が生じます。小学校の授業は14時半頃に終わってしまうことも多く、定期的に午前授業による早帰りなども発生するので注意しましょう。学童を利用することもできますが、基本的にお迎えが18時までと指定されているなど、フルタイム共働き家庭にとって大きなハードルとなっています。
また、小学校が始まるのは朝8時前後からであり、それより先に登校させることはできません。親の方が早く家を出てしまう場合、「ひとりで戸締りがしてでかけられるか?」「時計を見て正しい時間に家を出発できるか?」などの心配も出てきます。自分ひとりででかけられるようになったり、クラブ活動等で帰りが遅くなったりするのは高学年以降のため、低学年のうちはまだまだサポートが必要でしょう。
宿題や翌日の準備など学校生活のサポートをしやすいから
小学生になると、宿題や翌日の準備など学校生活のサポートが求められます。最終的には宿題や学校での活動を自分でこなせるようになるのが理想ですが、低学年のうちは親のサポートが欠かせません。音読チェックや宿題の丸付けなど、親に任される役割も大きくなります。ランドセルの準備、忘れ物チェックなども含めれば、意外とやることが多いと感じるでしょう。
時短勤務を続けて夕方以降の時間を確保できれば、宿題や翌日の準備など学校生活のサポートもしやすくなります。子どもと一緒にリラックスしながら宿題を進めたり、翌日の学校生活に備えて準備を手伝ったりできるので、翌日も安心して送り出せます。
PTA活動など平日イベントに対応しやすいから
授業参観・オープンスクール・親子教室などの学校イベントやPTA活動は、平日日中に開催されます。親が学校に足を運ぶ場面は意外と多く、子どもが主体の場所であるからこそ、保育園のように土日に開催するような配慮もほとんどみられません。仕事次第では「授業参観に行けない」「ボランティアに参加しながら自分の子の様子を見ることができない」など、デメリットに感じることもあるでしょう。
時短勤務にすることで、夕方の下校見守りボランティアに参加できるなど、フレキシブルな時間の使い方ができます。「親が学校で自分の姿を見ている」という安心感にもつながるので、子どものメンタルケアもしやすくなるかもしれません。
精神的な「小1の壁」に対応しやすいから
小学生になると一気に子どもの社会も広がり、新しい友達との付き合い方や学校ならではのルールなど、学ぶことも求められることも増加します。特に最初の数ヶ月は学校生活への適応にストレスを感じやすく、帰宅後に不安や疲れを感じることが多くなるので注意しましょう。登校渋りのある子には親が付き添い登校をして対処したり、友達トラブルがあれば相手の家庭に連絡したりする臨機応変さも必要です。
時短勤務であれば、子どもが学校から帰ってきた後、ゆっくりと話を聞く時間を確保しやすくなります。明確な困りごとを抱えていない子であっても、「親に話を聞いてもらえる」「親と遊んでストレスを解消できる」などの安心感を与えてあげるのが理想です。子どもが学校に慣れるまで毎日の支度や宿題チェックも手厚くサポートでき、精神的な安定につながるかもしれません。
平日の習い事や放課後の時間づくりがしやすいから
時短勤務の場合、平日の習い事や放課後の時間づくりがしやすいのもメリットです。小学校に入ると習い事を始める子が増え、スポーツ・音楽・学習塾など選択肢も拡大します。習い事は放課後の時間帯に集中していることが多いため、親の送迎・見守りなどを考えると仕事の調整が必須となるでしょう。習いごとのジャンルによっては自宅での自主練も必要なので、子どもに任せっぱなしにするのは不安に感じるかもしれません。
また、時短勤務をして少し早めに帰宅することができれば、子ども同士で公園に遊びに行くようなことが増えても安心です。急なケガやトラブルにも対応しやすい他、自宅に友達を招いて遊ぶなどフレキシブルな遊びの選択肢も与えやすくなるでしょう。放課後の時間を有意義に過ごさせるための大きな助けとなりそうです。
時短勤務できるのはいつまで?
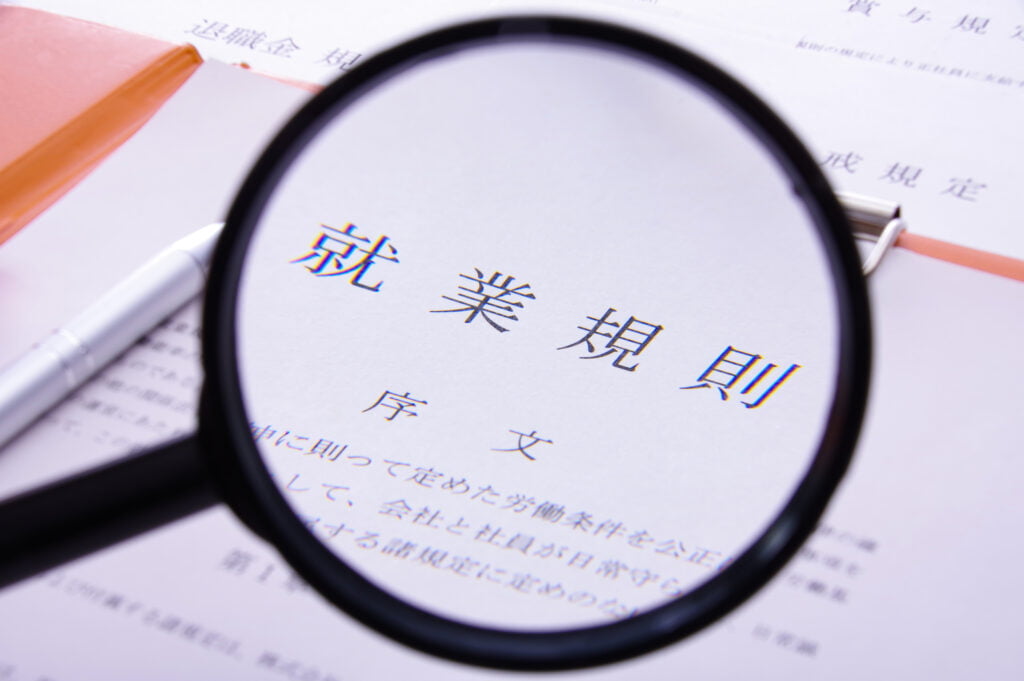
ここでは、時短勤務できるのはいつまでか詳しく解説します。今いる会社の就業規則と照らし合わせながらチェックしてみましょう。
法律上は「子どもが3歳の誕生日を迎える前日まで」
育児・介護休業法では、「子どもが3歳の誕生日を迎える前日まで時短勤務の取得を認めなくてはいけない」と規定されています(育児・介護休業法23条1項)。つまり、3歳未満の子がいる家庭の親から時短勤務を要望された場合、会社側は必ず対応する義務が課せられているのです。3歳までは確実に時短勤務できると考えてよいでしょう。
とはいえ、3歳以降の時短勤務に関する法律はなく、企業の裁量に任されています。まずは法律だけ遵守していればよいと考える企業がほとんどで、多くの企業で3歳までしか時短勤務できないことに注意が必要です。
企業によっては「小学校に上がるまで」などルールはさまざま
育児・介護休業法24条1項では、小学校就学の始期に達するまでの子を育てる労働者に対する措置として、時短勤務を認めるよう努力義務が課せられています。あくまでも努力義務であるため厳密に遵守する必要はありませんが、「せめて小学校入学まで時短勤務できるようにしよう」と独自のルールを設けている企業も少しずつ増えてきました。法律の枠組みを超えた+αの福利厚生であり、働くパパ・ママや介護と両立したい家庭向けの取り組みとして注目されています。
とはいえ、条件が緩和されてもなお「時短勤務できるのは小学校に上がるまで」となっていることが大半で、小学生になってからはフルタイムに戻るしかないケースがほとんどです。小1の壁にぶつかりやすい時期にフルタイムにしなくてはならず、ギャップを感じるかもしれません。
子供が小学生になっても時短勤務をする方法

最後に、子供が小学生になっても時短勤務をする方法を解説します。時短勤務に関する自社のルールが「3歳になるまで」または「小学生になるまで」だった場合、以下の方法で小学生以降も時短勤務できないか検討してみましょう。
会社に直談判する
小学生になっても時短勤務を続けるためには、会社に直談判して許可を得る必要があります。特に上司や経営者の裁量が多い会社であれば、鶴の一声でルールを緩和してもらえるかもしれません。会社の繁忙期や人員状況などを考慮して問題なければ、時短勤務の延長も認められます。
とはいえ、就業規則で時短勤務ができるのは「3歳になるまで」または「小学生になるまで」と認められている場合、自分ひとりの声で特別ルールを適用してもらうのは難しいのが現状です。会社側には後々の不公平につながらないようにする義務があるからこそ、簡単に決断できない事情もあるでしょう。
あくまでも直談判は相談ベースでおこない、無理な要望にならないよう配慮する必要がありそうです。
フレックスタイム制度やリモートワークで代替する
どうしても時短勤務期間の延長ができない場合、フレックスタイム制度やリモートワークで代替するのがおすすめです。フレックスタイム制度を使えれば出退勤の時間を自由に調整できるため、家族で協力しながら子の生活に伴走することができます。リモートワークができれば自宅がそのままオフィスになるため、子の帰宅を家で迎えられるのがメリットとなるでよう。いずれも急なトラブルや通院に対応しやすい手法で、働くパパ・ママの貴重な選択肢となっています。
自社にフレックスタイム制度やリモートワークの仕組みがあれば、遠慮なく活用しましょう。どのような時間帯に、どのような場所で、どのように仕事を進めるのか、シミュレーションしておけば切り替えもスムーズです。
時短勤務期間が長い(または制限がない)会社に転職する
会社への直談判もできなさそうで、フレックスタイム制度やリモートワークが使えない(代替できない)場合、時短勤務期間が長い会社に転職するのが解決案となります。なかには時短勤務できる期間に制限を設けていない会社もあり、子どもが高学年や中高生になっても時短正社員として勤務し続けられます。少なくとも小学生の間だけでも時短勤務を続けられれば、親の精神的な安心にもつながります。
とはいえ、転職直後から時短勤務できる会社はまだまだ少ないのが現状です。多くの場合、「勤続1年以上の社員を対象に時短勤務を認める」など条件がついているため、転職直後はフルタイムでいる必要がある点に注意しましょう。
転職直後から時短勤務したいときは、時短正社員特化型の転職エージェントを頼るのがおすすめです。すぐにでも時短勤務できる数少ない求人が集中しているので、効率よく求人を探せます。
まとめ
時短勤務できる期間は、ほとんどの会社で「子が3歳になるまで」と定められています。少し延長できる会社でも「子が小学校に上がるまで」と指定されていることが多く、小学生以降も時短勤務できる会社はまだまだ少ないのが現状です。
リアルミーキャリアでは、小学生以降も時短勤務でき、かつ転職直後から時短勤務を始められる求人を数多く扱っています。その他、フレックスタイム制度やリモートワークができる企業の求人も多いので、働き方を見直したい方はぜひご活用ください。


