時短勤務なのに残業ばかり!残業強制は違法なの?残業代の計算はどうなる?
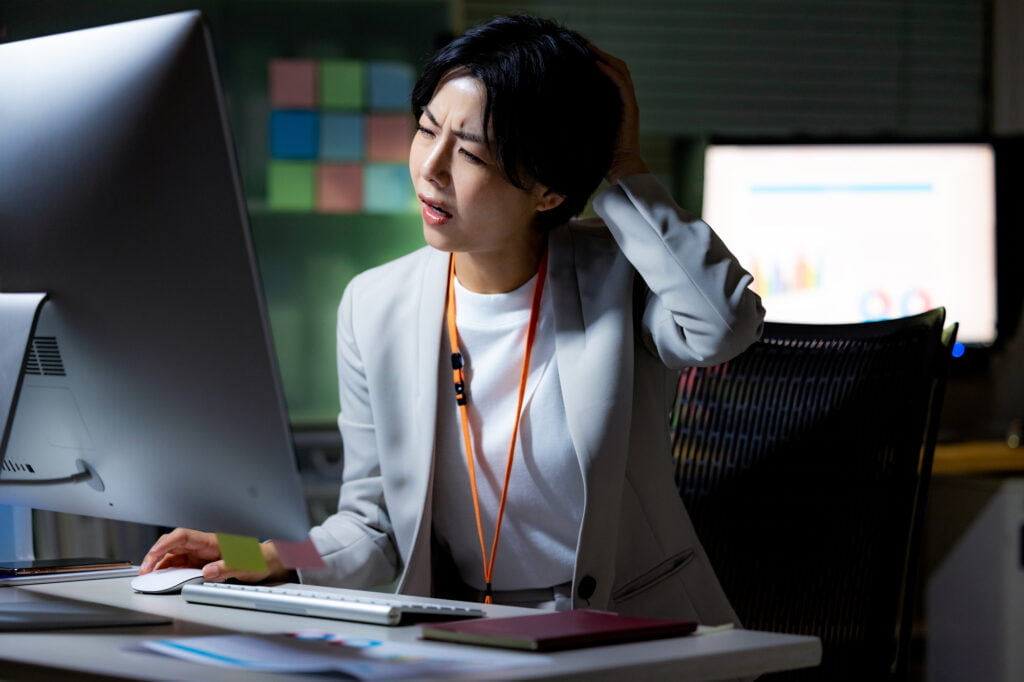
本来、時短勤務は退勤後に続く家事・育児・介護・療養・プライベート時間などを充実させるための働き方です。
時短勤務でも残業できるとはいえ、残業ばかりな毎日になると時短勤務している意味を見いだせなくなるので注意しましょう。とはいえ、会社側の命令によりやむを得ず残業をしなくてはいけず、悩んでいるワーママが多いのも事実です。
今回は、時短勤務なのに残業ばかり命じられる場合の対処法を解説します。また、残業代の計算方法にも触れるので確認してみましょう。
もくじ
なぜ時短勤務なのに残業が発生するのか?
そもそも、なぜ時短勤務をしているのに残業が発生するのでしょうか?いくつか原因を考えてみましょう。
能力に対する期待から
産休取得前で成果を出していた、能力を評価されていた方は、復帰後も同様の成果を期待されるケースがあります。業務を効率化しても、以前と同じ成果を出すのはなかなか難しくやむなく残業することもあるでしょう。
難しいのは、会社側からの期待だけではなく、労働者本人もキャリア志向があり「仕事量を抑制してほしい」と言い出しづらいことです。
仕事は有能な人のところに集まるとはよく言われますが、労働者自身も育児と両立する期間はどこかで線引きをするか、人員体制の変更や分業による根本的な業務改革を行っていく必要があるでしょう。
女性活躍の文脈から
これも能力への期待に近い内容ですが、近年は女性活躍に注目が集まっているため、昇進するワーママのモデルケースを企業が求めることが増えています。
労働者本人は希望していないが会社がモデルケースを作りたいがために過剰な期待を寄せてしまい、それが残業につながることもあるでしょう。
業務工数の見積もりの難しさから
仕事は定型業務ばかりではありませんから、職種によって業務工数の見積もりが難しい場合もあります。また、業務のスピードも個々人によって異なるため、会社側としてもどれぐらいの仕事を任せればいいかわからず、知らず知らずのうちに残業を押し付けてしまっているということがあるでしょう。
この場合、労働者としてはこまめに上司等に相談し、業務量を調整してもらう必要があります。最初からきれいに適切な業務量を渡すことは難しいでしょうから、軌道修正を前提とすることです。
残業体質の会社だから
会社全体がそうである場合もありますし、部署や特定の仕事がそうである場合もあります。
部署や仕事内容に依存している場合や、育休からの復帰時に異動することで回避できます。会社全体が残業体質である場合は、やはり転職が現実的な選択肢になってくるでしょう。
時短勤務の人に残業を命じるだけでは違法にならない

結論からお伝えすると、時短勤務の人に残業を命じるだけで違法性が問われることはありません。
残業は業務スケジュールに応じてやむを得ず発生するものであり、時には時間の都合をつけてでも対応すべき案件があるのも事実です。時短勤務制度とはあくまでも所定労働時間を短くする効果があるだけで、残業について規制するものではありません。
会社からの命令があれば原則として断ることはできず、従業員同士で協力しながら乗り越えるべきものと言えるでしょう。
この対象には時短勤務している人も含まれており、会社で働く以上、会社からの業務命令には従う必要があるのです。
残業命令が違法になるケース

残業命令をすること自体は違法でないものの、命令の方法・内容次第では違法性に問われることがあります。
特に、下記に該当する残業命令が常態化している会社は、要注意と考えてよいでしょう。
法定労働時間または36協定の範囲を超えて残業を命じる場合
法定労働時間を超えた残業時間数を命じるのは、原則として違法です。
ここでの法定労働時間とは「1日に8時間(または1週間に40時間)を超えた労働」のことを指し、時短勤務の有無に関わらず、従業員をこれ以上働かせることはできないのです。
時間外労働協定(36協定)を労使間で締結している企業であれば、この上限が引きあがるので残業させることができますが、それでも残業時間の上限は原則として「月45時間(または年360時間)まで」と定められています。
労働時間が長くなると過労・体調不良・メンタルバランスの悪化などにつながるので、注意しておきましょう。
免除申請が出ている人に残業を命じる場合
残業免除申請が出ている人に対し、残業を命じるのもNGです。
その名の通り残業を免除してほしいからこそ提出されているのが「残業免除申請」であり、会社側が受理した以上、一方的に残業を命じることはできません。
なお、残業免除申請は「所定外労働の免除」と呼ばれることもあり、育児・介護休業法第16条の8第1項にて定められている権利です。
「3歳未満の子を養育している従業員から請求があった場合には、事業主は事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならない」と制定されています。
「事業の正常な運営を妨げる場合」の定義は明確な線引はありません。ただ、事業内容、労働者が担当する仕事内容、代替要員の有無などを考慮して客観的に判断されるものとなっています。
その他、家族の介護・透析など自身の療養のため残業免除申請を出す方もいます。
時短勤務者が残業する場合の落とし穴

時短勤務者であっても都合のつく範囲で残業に協力すべきとはいえ、思わぬ落とし穴があることも事実です。
ここでは代表的な事例を紹介するので、「時短勤務しているから」と安心しきらないよう目を通していきましょう。
残業の割増手当がつかない場合がある
時短勤務者が残業した場合、残業の割増手当がつかない場合があるので注意が必要です。
通常、残業をすれば1.25倍の割増手当がつきますが、これはあくまでも法定労働時間を超えて働く場合の手当です。
時短勤務により6時間しか働かない人が1時間残業したとしても、法定労働時間である8時間を超えないため、企業側に割増手当をつける義務はありません。
もちろん8時間を超えて残業する場合は割増手当がつきますが、短時間の残業では「割に合わない」と感じることもあるでしょう。
とはいえ、時短勤務者が残業する場合、延長保育料金・ファミサポの利用代・ベビーシッターに支払う依頼料などが嵩みやすいのは事実です。
「残業をして稼げる金額より、残業に応じたことによる支出の方が大きい」となっては本末転倒になるかもしれません。
子どもが3歳を迎えると残業の免除申請ができない
前述した通り、育児・介護休業法第16条の8第1項にて定められている「所定外労働の免除」制度は、3歳未満の子を養育している人を対象としています。
つまり、子どもが3歳を超えた場合、残業の免除申請ができなくなり時短勤務であっても残業せざるを得なくなる可能性があるのです。
企業独自の社内制度として長期間の残業免除申請を受理してくれる会社もありますが、まだまだ数は多くありません。
子どもが3歳を超えてもまだ手がかかることを考えると、残業の頻度・時間次第ではワークライフバランスを崩してしまいかねないのです。
残業の免除申請に関わる具体的な法的手続きはない
残業の免除申請に関する具体的な法的手続きはなく、あくまでも従業員と企業間における自発的なやり取りとなっています。
産休・育休のように健康保険組合やハローワークを通さないので、「そもそもうちにそんな制度はない」と誤解されたり、「どうやって手続きするのかわからない」と言われたりすることもあるでしょう。
また、書類のフォーマットが用意されていなかったり、手続きが形骸化していて実質的に残業が減るとは限らなかったりするケースもあります。
そのため、「せっかく制度があっても意味がない」と感じるかもしれません。
上司・同僚から理解されない会社もある
残業の免除申請は働く人の権利とはいえ、どの会社でも必ず理解されるとは限りません。
「家事や育児を工夫すれば多少の残業くらいできるのでは?」「周りは苦しいなかでもどうにか残業して会社に貢献しているのに、ひとりだけ特別扱いすることはできない」と思われてしまうこともあるでしょう。
あからさまに冷遇されることがなくても、何となく居心地の悪さを感じることもありそうです。
他のワーママが夫や親戚の協力を得てなんとか残業している場合や、過去に残業免除申請を受けた事例がない会社では、より溝が感じられそうです。
時短勤務なのに残業が多すぎるときの対処法

時短勤務なのに残業が多すぎると感じる場合は、早めの対応が大切です。
なんとか無理してこなしているうちに、「あの人は残業できる人」「去年大丈夫だったから今年も平気だろう」と思われてしまうかもしれません。
ここでは、残業が多すぎるときの対処法を解説します。
上司・経営者・先輩社員に直談判する
まずは、上司・経営者・先輩社員などに相談するのがおすすめです。
業務量の調整・部署異動・同僚との業務分担・業務効率化による作業時間の短縮・アルバイトなどの増員を検討してもらえるかもしれません。
自分ひとりではできない戦略的な残業予防策を講じてもらえる可能性も高く、会社全体にとっての利益につながります。
しかし、全ての会社が従業員の声に耳を傾けてくれるとは限りません。
「簡単に異動させることはできない」ときっぱり断られたり、従業員を増員したくても予算の都合でどうにもならなかったりする企業も多いです
残業の免除申請を提出する
子どもが3歳以下であれば、思い切って残業の免除申請を出すのもひとつの方法です。
既に利用実績のある会社では受け入れられやすく、会社から許可をもらっているからこそ残業を断りやすくなる効果も発揮されます。
後ろめたさを感じることなく退勤できるので、精神的にも負担が軽くなるでしょう。
ただし、子どもが3歳を超えたときの対応は、別途考えておく必要があります。
短期的に残業時間を抑えたいのであれば有効ですが、既に子どもが3歳を超えている家庭や数年単位で残業を抑えたい家庭にとっては有効でないかもしれません。
持ち帰り残業・早出残業をする
保育園のお迎えや学童を終えた子どもの留守番時間が気になるのであれば、持ち帰り残業させてもらうのもひとつの手段です。
残業する負担自体は変わりませんが、一旦は家庭に戻ることができるので、子どもに与える影響は最小限で済むでしょう。
また、夫と協力しながら早出残業をして、朝活を兼ねて早い時間帯に業務を終わらせてしまうのもひとつの手段です。
ただし、持ち帰り残業の量が多すぎて睡眠時間が極端に削られたり、子どもの前でもずっと仕事をしなくてはいけない環境が続くのであれば、却って効率が妨げられてしまいます。
また、家庭の状況次第では早出残業できないケースもあるので、スケジュールをチェックしてみましょう。
フルタイムで働く
都合が許すのであれば、フルタイムに戻すのも選択肢のひとつです。
フルタイムであれば「時短勤務なのに残業が多い」という悩みを払拭でき、そもそも残業があることを前提に働けます。
残業した時間にはそのまま割増手当が乗るので、金銭的にもメリットの多い方法と言えるでしょう。
しかし、保育園や学童の都合によっては、そもそもフルタイムで働けないワーママが多いのも事実です。
また、フルタイムができる環境であっても、子どもとの時間を十分に確保したいためあえて時短勤務にしている方もいるでしょう。
フルタイムに戻しても残業自体を抑制する効果はないので、慎重に検討する必要がありそうです。
法的に訴える
「会社が残業免除の申請を認めてくれない」「残業免除申請をしたのに残業を強制される」などの法律違反がある場合は、法的に訴えることもできます。
厚生労働省管轄の労働基準監督署では働く人からの声に応じて監査や指導をしてくれるので、相談してもよいでしょう。
しかし、ひとりの声だけで即座に指導が入ることは少なく、残念ながら迅速性がないことも多いです。
また、「〇〇さんが労働基準監督署にタレコミした」と社内で噂されたり、「そこまで残業が嫌なら辞めればいいのに」と陰口を言われたり、心無い対応をされてしまうこともあるでしょう。
もちろん残業免除申請を出したことが原因で冷遇するのも法律違反ですが、居心地の悪さが高まる可能性があるので諸刃の剣と言えそうです。
それでも残業が減らない場合に検討すべき転職先は?

どうしても自社の残業体質が変わらなさそうであれば、勇気を出して転職する方法もあります。
しかし、応募先の情報をしっかりリサーチしておかないと、転職先でも似たような残業命令ばかりになることがあるので注意しましょう。
ここでは、残業に困っている方が検討すべき転職先を紹介します。
基本的に定時退社を徹底している会社
基本的に定時退社を徹底している会社であれば、時短勤務でもフルタイムでも時間通りに退勤できます。
退勤後の予定も立てやすく、保育園や学童のお迎え時間が日によって変動することもありません。
日によっては夕方の予防接種や習い事の付き添いに行けるなど、勤務後の自由度が高まります。
また、基本的に定時退社な会社であれば、やむを得ず残業が発生してしまったときの不満度も高くなりません。
「残業が常態化しているか」をひとつの基準に設けて、転職先を選定していきましょう。
期限を問わず残業免除申請を受け付けている会社
期限を問わず残業免除申請を受け付けている会社であれば、子どもが3歳を超えても小学生になっても残業しなくてよくなります。
長く働けば働くほど周りの理解も深まっていくので、腰を据えて働ける環境を希望する場合に最適です。
また、ワーママだけでなく介護や療養で制度を利用する人も多くなるので、人材の定着率も上がります。
同僚の急な退職や慢性的な人手不足に悩まされることもなく、安定した働き方が叶うかもしれません。
テレワーク導入中の会社
テレワークを導入している会社であれば、やむを得ず残業する場合でも極端に子どものお迎えが遅くなることがありません。
また、時間を問わず対応できる業務であれば寝かしつけ後や土日でも働きやすく、自分のペースを守れます。
通勤時間がないため時間を有効活用できるなど、残業以外のメリットも多いので注目しておきましょう。
フレックスタイム制度を導入中の会社
フレックスタイム制度を導入している会社であれば、事前の申請時間に合わせて働きやすくなります。
夫の協力が期待できる日だけ残業したり、どうしても残業できない日は少しだけ早めに出勤したり、柔軟な時間の使い方ができるでしょう。
ワーママに限らず他の従業員も自由に働いていることが多く、遠慮なく制度を使える点も魅力です。
ワーママが多い会社
ワーママが多い会社であれば、残業を減らしたい気持ちを理解してもらえる可能性が高いです。
お互いのために協力し合いながら業務を分担したり、時には残業を代わり合ったりできるかもしれません。
家庭環境ごとに理想的な働き方が異なることを理解してくれる職場であれば、ワーママ同士の多様性も認め合えます。
会社次第で働きやすさや残業の苦しさが大幅に変わることを理解しながら、転職先を選んでいきましょう。
まとめ
時短勤務なのに残業がなくならない場合、上司や経営層に相談したり残業免除申請を出したりするのがおすすめです。
それでも思うような働き方ができないときは、思い切って転職し、無理なく働ける環境を整えてもよいでしょう。
リアルミーキャリアは、時短正社員転職を目指すワーママ特化型の転職エージェントです。
残業の少ない会社・テレワークやフレックスタイム制度を導入済みの会社も多く集まるので、自分に合った働き方を模索したいときはお気軽にご相談ください。


