子供が欲しいけど転職もしたい!赤ちゃんと仕事どちらを優先する?

子供が欲しいけど転職もしたい場合、どちらを優先するべきか迷ってしまう方は多いのではないでしょうか。子どもは理想的なタイミングで必ずしも授かれるものではなく、つわりや定期的な通院も考えると仕事との両立がしづらくなります。転職も、転職したいタイミングで理想的な求人が見つかるとは限らず、職場に馴染むまでの期間も含めると転職活動のはじめ時に迷いが生じるものです。
本記事では、子どもが欲しいけど転職もしたい方に向けて、解決のためのヒントを解説します。
もくじ
出産と女性のキャリアに関する現状

まずは、出産と女性のキャリアに関する現状を解説します。他の女性たちがどうキャリアとライフイベントのバランスを取っているのか、参考にしてみましょう。
初産の平均年齢は31.0歳
(※)参考:人口動態調査|厚生労働省
厚生労働省の調査によると、2023年には初産の平均年齢が31.0歳に到達しました。1985年には25.7歳であったため、直近の20年の初産の平均年齢が約5歳近く上昇していることがわかります。世界各国と比較しても日本の初産年齢は高い方で、女性の社会進出やキャリア志向の高まりが背景にあると分析されています。
なお、このデータはあくまでも「初産」の平均年齢を可視化したものであり、第2子・第3子を産む母親の年齢はさらに高くなっているだろうと予想できます。30代になると仕事でも責任のある立場に就くことが増え、後輩の面倒を見たり昇進・昇給したりすることが増える時期でもあるため、妊娠のタイミングに迷う人も多くなります。
育児休業取得率は女性85.1%・男性13.9%
(※)引用:図表1-8-1 育児休業取得率の推移
厚生労働省が2022年に実施した調査によると育児休業取得率は女性85.1%・男性13.9%でした。女性の育児休業取得率は過去10年間ほぼ横ばいであるのに対し、男性の育児休業取得率は増加を続けています。厚生労働省も男性の育休取得を促進しており、「パパ・ママ育休プラス」制度の開始や企業への呼びかけに呼応して、まさに今少しずつ社会が変わっている様子が伺えます。
パパもママも安心して育休を取れる社会になれば、女性のキャリア構築もしやすくなります。パパが育休を取っている間に転職活動をするなど、フレキシブルなキャリアパスを描けるようになるでしょう。
第1子出産後も53.1%が仕事を続けている
(※)引用:女性の継続就業と子育て支援
内閣府の資料を見てみると、第1子出産後も53.1%の女性が仕事を続けているとわかります。出産前から仕事に就いている人のうち、第1子出産後に「就業継続(育休なし)」と「就業継続(育休利用)」を選択した人の割合は年々少しずつ上がっており、2010年から2014年の調査では過半数を超えることとなりました。
一方、出産前から仕事をしていたにも関わらず、出産を機に退職してしまった人も33.9%存在します。自ら希望して退職したのでない場合、産後のキャリア形成や社会とのつながりを失うことになりやすく、再就職も難しくなることが懸念されます。
子供が欲しいと感じたときにやるべきこと
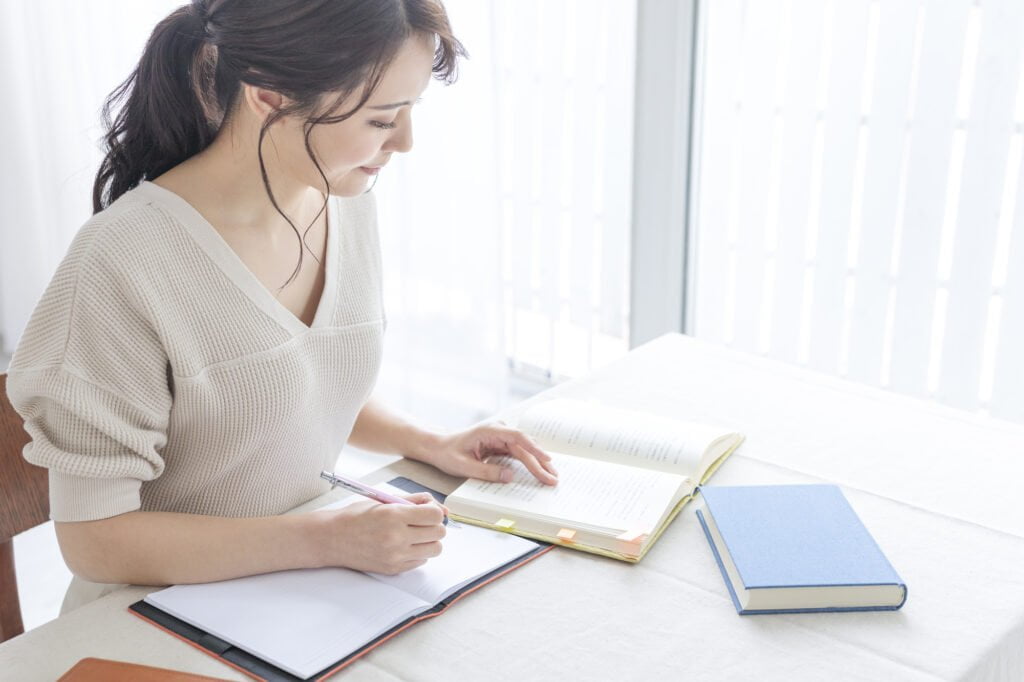
ここでは、子供が欲しいと感じたときにやるべきことを解説します。仕事と妊娠・出産のバランスを取るためにも、事前に対策できる点は対策しておきましょう。
1.自社の就業規則や福利厚生を確認する
まずは、自社の就業規則や福利厚生を確認します。産前産後休業や育児休業に関するルール、最長で何年何ヶ月仕事を休めるのか、いつまで残業免除や時短勤務を申請できるのか…など、ルールを細かく把握しておく必要があります。また、妊娠・出産について報告するフローや、過去に産休育休を取った先輩ワーママの事例を調べておくのもよいでしょう。同じ部署など近い距離に先輩ワーママがいる場合、直接話を聞いてみるのもおすすめです。
また、復帰後に使える勤務形態を調べ、時短勤務・フレックスタイム制度・リモートワークなど、働き方別の生活をシミュレーションしておく必要もあります。企業によってはより自宅から近いオフィスに異動願を出せるケースもありますが、希望を出したからといって100%その通りになるとは限らない点にも注意が必要です。
2.ライフイベントの優先順位を決める
「子供を産み育てる」というのは人生における大きな転機になることが多く、仕事・キャリア・経済状況など他のライフイベントと密接に関わってきます。方針がブレないようにするためにも、夫婦でよく話し合い、ライフイベントの優先順位を決めておきましょう。
例えば、年齢を考えて少しでも早く出産しておきたい場合、転職より出産が優先されます。反対に、産休育休から復帰した後のキャリアを考えて、出産を急がないでおく選択肢もあるでしょう。他にも、マイホームやマイカーの購入、親の介護など、考えておかなくてはいけないライフイベントが多いときは注意が必要です。
3.長期的なキャリアを可視化する
妊娠出産前後のキャリアだけでなく、長期的なキャリアも可視化しておきましょう。できる限り今の会社で長く働きたいのか、条件次第では積極的に他社へ転職することも視野に入れているのかなど、方針によりキャリアのイメージも変動します。妊娠出産前にどのようなスキルを磨いておくべきか、どのような経験を積んでおくべきかなど、具体的に考えるきっかけにもなります。
また、「将来は自分で会社を立ち上げたい」「ゆくゆくはフリーランスとして独立したい」などの方針を抱くのであれば、出産のタイミングも重要です。重要なライフイベントが一気に押し寄せてパンクしてしまわないよう、対策しておきましょう。
4.夫婦で同じイメージを共有しておく
キャリアプランや妊娠出産に関する理想は、夫婦でしっかり共有しておくことが大切です。将来の育児や生活に対する考え方を統一できるので、いざ妊娠出産を控えてから混乱することもありません。「子供が生まれたらパパも育休を取る」「本格的に妊活するのであればパパも転勤のない会社に転職する」など、対策も千差万別です。反対に、パパは全力で仕事をして、ママが子育てに集中できる環境にする家庭もあります。
育児は時に困難を伴うものです。事前に共通の認識を持っておくことで、困難な状況に直面した際にも、協力して乗り越えやすくなるでしょう。
5.両親や周囲のサポート体制を確認する
事前に、両親や周囲のサポート体制を確認しておくこともおすすめです。両親が近くに住んでいて健康状態がよく、仕事を引退していて時間があるなど比較的手を借りやすい状態であれば、事前に相談しておくことで快く育児に協力してもらえるかもしれません。反対に、気軽に頼れない状態・距離感であれば、他の親戚を頼ったり、なるべく夫婦だけで乗り越えられる体制づくりが欠かせません。
また、今住んでいるエリアの保育園情報を調べておくなど、保活を視野に入れておくのも効果的です。あまりにも激戦区で入園が厳しそうな場合、無理のない範囲で事前に引っ越しておくのもよいでしょう。その他、産前産後健診の補助、妊娠期間中に使える制度、ファミリーサポートなど産後に使える制度を調べておき、子育てのしやすさをチェックしておく方法もあります。
【ケース別】子供が先か?転職が先か?

ここからは、ケース別に「子供が先か?転職が先か?」を検証していきます。自分のケースと照らし合わせながら、後悔のない選択ができるよう情報収集しておきましょう。
①今の会社に充実した福利厚生・働き方がある場合
今の会社に充実した福利厚生・働き方がある場合、子供を優先して問題ありません。すぐに妊娠・出産しても最大限サポートしてもらえる可能性が高く、使える制度をフル活用して安心して出産に臨めます。フレックスタイム制度やリモートワークなどフレキシブルに働ける制度がある会社、子育て手当金など金銭的な福利厚生が充実している会社、子育てに理解があって仕事を休むことがあってもお互い様な社風が根付いている会社の場合、より安心できます。
転職を希望する場合、子供が生まれてある程度落ち着いてからでもよいでしょう。子供の年齢に合わせた働き方を望む場合、そのタイミングで改めて転職を検討できます。
②年齢的に今すぐにでも子供が欲しい場合
年齢的に今すぐにでも子供が欲しい場合も、子供を優先しましょう。授かりたいタイミングで100%授かれる保証がないからこそ、早めに妊活を始めて理想に近づけていく必要があります。想像以上に長く授かれなかった場合、キャリアプランやライフプランにも影響するので、早めのスタートで損することはありません。
転職は、産後ある程度落ち着いてから再度検討することとなります。転職した直後は妊活しづらいことを鑑みると、よほど子育てしづらい会社でない限り、転職を急ぐ必要はありません。
③今の会社に充実した福利厚生・働き方がない場合
今の会社に充実した福利厚生・働き方がない場合は、転職して働きやすい環境を確保する方を優先します。例えば、無事に希望のタイミングで妊娠できたとしても、マタニティハラスメントを受けて退職せざるを得なくなるのではその後のキャリアに支障が出てしまいます。同じく、残業・出張・休日出勤が多くて物理的に産後の育児と両立できなさそうな場合や、どう頑張っても夫婦間での役割分担ができない場合も、安心して子育てすることはできません。
思い切って早めに転職し、福利厚生や柔軟な働き方を求める方法もあります。妊娠出産はゴールではなく、その後の生活が長いことを考えると、安心できる生活基盤を作っておくことも大切です。
④本格的な不妊治療に踏み切りたい場合
本格的な不妊治療に踏み切りたい場合も、先に転職して働きやすい環境を確保するのがおすすめです。不妊治療と仕事を両立できるかは、企業の社風により大きく変化します。フレックスタイム制度やリモートワークが使えたり、理由を問わず取得できる休暇制度が充実していたりする会社であれば、負担の大きい不妊治療中も仕事を辞めずに続けられるでしょう。反対に、不妊治療に対する理解がない会社や、激務で休みづらく業務上の負荷が大きい会社の場合、不妊治療中の大きなストレスになりかねません。結果的に仕事を辞めざるを得ないなど、キャリアの断絶も起こります。
転職して働く環境を整えておくことで、妊活にも集中しやすくなります。既に妊活を始めていて、仕事との両立に悩んでいる人も、転職を検討してみましょう。
子どもを先に産むメリット

ここからは、子どもを先に産むメリットと転職してから子どもを産むメリットを解説します。まずは子どもを先に産むメリットからチェックしてみましょう。
年齢的な制限を気にしなくてよい
一般的に、妊娠出産のリスクは年齢が上がるにつれて高まると言われています。「若い方が出産後の体の回復が早い」「年齢が上がると妊娠しづらくなる」など、周りから言われて悩んでいる人も多いのではないでしょうか。早い段階で妊活しておけば、妊活が長期化したときの負担も少なく、ライフイベントの計画も立てやすくなるのがメリットです。
体力的な余裕ができる
育児は体力勝負な面もあるため、少しでも若いうちに子供を産んで体力的な余裕を持っておきたいという方は多いです。産後に回復しやすいことはもちろん、その後も続く夜泣き対応や休日のレジャーも、体力があるに越したことはありません。
また、比較的若い年齢で子育てを始めることで、子どもとの時間をより長く楽しめるのもメリットです。自分の健康状態の心配がなく、元気に子供と走り回れる期間は、後で思い返してみてもかけがえのないものとなるでしょう。
柔軟なキャリアプランを描ける
出産が早いと、その後に柔軟なキャリアプランを描けるのがメリットです。育児を通して得た経験やスキルを活かしたキャリアを模索したり、働き方を変えたりするなど、柔軟なキャリアプランを立てることも可能でしょう。また、当初描いていたキャリアプランから大きく方向転換する場合でも、若い段階で決断した方がその後の余裕が生まれます。
育児を通して、自分の強みや弱み、本当にやりたいことなど、自己理解が深まるケースは少なくありません。自己理解に基づいたキャリアプランを立てることで、より満足度の高い働き方を見つけられます。
転職してから子どもを産むメリット

次に、転職してから子どもを産むメリットを解説します。以下を重視する方は、転職を優先させましょう。
今以上に福利厚生・働き方が充実した会社を目指せる
転職により、今以上に福利厚生が充実した会社を目指せるのが最大のメリットです。特に今の会社の福利厚生に不満があるときや、働き方に柔軟性がなく産後の両立が厳しくなりそうなときは、転職しておくとよいでしょう。
例えば、育児休業中の給与補填制度・出産祝い金・育児支援金など、経済的なサポートが手厚い会社を選べば金銭的な不安も軽減できます。同様に、時短勤務制度や子の看護休暇など、育児と仕事を両立するための制度が整っている会社を選べば柔軟な働き方ができるでしょう。
育児と仕事のバランスを取りやすい環境の会社を選ぶことで、より充実した生活を送れます。出産後に転職するのは大変そうだと感じる人も、先に転職して問題ありません。
産後のリモートワーク等を視野に入れられる
転職して柔軟な働き方ができる会社に入れば、産後のリモートワーク等を視野に入れられます。産後は体調が不安定になりやすく、通勤の負担を減らすことは、心身の健康維持につながります。子どもの体調不良や急な用事にも対応しやすく、日によっては子どものそばで仕事ができるなど、安心できる点も多いです。
リモートワークの他、フレックスタイム制度を活用することで夫婦での役割分担をしやすくする方法もあります。どんな働き方を採用しているかは、業種・職種・企業により異なるので、転職を視野に入れて少しずつ情報収集してみることをおすすめします。
出産後のキャリアプランを立てやすくなる
先に転職しておくことで、出産後のキャリアプランを立てやすくなるのもメリットです。「産後に転職しなければ」というプレッシャーから解放されるので精神的な安定にもつながり、10年スパンでのキャリアプランも立てられます。産後も長く働く前提で会社を選べば、出産・育児後の働き方を具体的にイメージし、将来のキャリア目標をより明確に設定する転職活動となるでしょう。
出産より先に転職する場合のポイント

ここでは、出産より先に転職する場合のポイントを解説します。転職のコツとしてお役立てください。
若い段階で転職した方が有利になりやすい
転職市場においては、若い人材の方がより有利になりやすいのが現状です。もちろん40代以降のハイスキル・ハイキャリアな人材を求める企業もありますが、子育てとの両立を前提とするのであれば若い段階で転職しておくのがおすすめです。「ゆくゆくは妊娠出産も考えている」と伝えたときも、10年後の育成まで視野に入れて採用してもらえるかもしれません。反対に、年齢が高くなりすぎるとその後のキャリアイメージがしづらくなり、採用担当者も二の足を踏んでしまうことがあるので注意しましょう。
妊娠希望時期から逆算して計画的に転職する
妊娠希望時期から逆算して、計画的に転職することが大切です。例えば、ゆっくり転職活動をするつもりで先に退職し、退職中に妊娠が判明した場合、転職のハードルはかなり高くなります。無職のまま妊娠出産するため産後に保育園を利用することもできず、職歴に大きなブランクが空くことになるでしょう。同様に、現職に在籍したまま転職活動している間に妊娠が判明したときも、一度転職を取りやめて出産に集中するケースが多いです。
うまくいくかわからない妊娠出産だからこそ、希望時期から逆算して計画的に転職する必要があります。転職は妊娠と違って先の見通しが比較的立てやすいので、まずは仕事面の環境を整えておきましょう。
産休・育休制度や復職支援制度が充実している企業を選ぶ
転職の際は、産休・育休制度や復職支援制度が充実している企業を選ぶことが大切です。子育てとの両立を前提に転職する以上、「転職できればどこでもよい」というわけにはいきません。福利厚生、フレキシブルな働き方、育児への理解、ワーママ率の高さ、社風など、総合的に判断して理想に近い会社を見つけてみましょう。
とはいえ、全ての条件を満たす会社があるとは限りません。希望する条件に優先順位をつけ、効率よく転職するのがポイントです。
転職エージェントなどプロを味方につけて転職する
転職エージェントなど、キャリアのプロを味方につけて転職することも検討しましょう。特に子育てに最適な環境を求めて転職する場合、フレックスタイム制度・リモートワーク・時短正社員など、希少性の高い求人を求めることとなります。フレキシブルな働き方やワークライフバランスを求める若い世代や、介護・療養との両立を目指す人、ハイスキルで実績のある人とも同じ土俵に立たなくてはいけないため、時に転職活動は難航するかもしれません。
転職エージェントのキャリアアドバイザーを頼れば、自分の強みを活かして転職できる求人を優先的に紹介してくれます。特に時短正社員転職やワーママ転職に強い転職エージェントであれば、妊活計画や産後の働き方も視野に入れたサポートをしてくれるのがメリットです。
転職直後の妊活は避けた方が無難
転職を優先するキャリアプランは非常におすすめですが、一方で転職直後の妊活は避けた方が無難です。転職直後に妊娠が判明した場合、組織に馴染む間もなく出産を迎えるため、復帰する際のハードルが高くなります。転職直後は新しい仕事に慣れるための期間であり、まだ会社やチームに貢献しきれていない段階で長期間の休業に入ってしまうと、自分自身の居心地も悪くなるでしょう。妊娠初期はつわりなど体調が不安定になりやすく、転職早々に欠勤ばかりが続くことも懸念されます。
スキル面でも社内の人間関係の面でも、ある程度の基盤を築いてから妊活する方が安心です。
産休中・育休中の転職も可能
仕事と子育ての両立を目指す場合、産休中・育休中の転職も可能です。労働基準法により、労働者が妊娠・出産・育児休業を取得することを理由に解雇したり、不利益な取り扱いをしたりすることは禁止されています。退職・転職も自由であり、産休中や育休中でも制限を受けることはありません。産休中に転職してもすぐ出産を迎えることになりますが、育休中で、かつ保育園など子供の預け先を確保できている場合は比較的転職しやすくなるでしょう。
育児に専念している期間は、自分のキャリア観や今後の働き方について深く考える期間としても活用できます。育児と仕事の両立を前提とした企業を探すなど、より明確な条件で転職活動を進めることも可能です。必要であれば転職エージェントなど専門家のサポートを受けながら、理想的なタイミングで転職するのがおすすめです。
子供も仕事も追い求めて成功した体験談

最後に、子供も仕事も追い求めて成功した体験談を紹介します。ライフイベントには「正解」がないからこそ、時には他の人の意見も参考にしながら、自分にとっての理想を探していく必要があります。
妊活に期限を決めて転職を優先した体験談
(Tさん 29歳 Webデザイナー)
結婚してすぐに子供が欲しいと思っていたけれど、会社が薄給激務だったため良い条件の会社に絶対転職したいと思っていました。
結婚が決まってすぐから妊活を始めたもののなかなか子供に恵まれなかったので、あと半年妊活して赤ちゃんができなかったら、いったん妊活をやめて転職を優先しようと決意しました。
妊活をやめてからは転職活動に集中し、今よりも良い条件の大手企業に転職することができました。この会社はワーママは採用していないとのことだったので、出産前に入社することができてラッキーでした。
転職後1年2ヶ月経って妊娠が判明し、無事に産休・育休に入ることができました。今は復帰して時短勤務で働いています。時短勤務でも前職よりも給料がアップしているので、出産前に良い条件の会社に転職できてよかったなと思っています。
妊娠出産を優先し、育休後に転職した体験談
(Kさん 38歳 マーケティング職)
とても激務な会社だったので、残業のできないママたちは補助的な仕事しか任せてもらえない様子をずっと見てきました。出産前にプロダクトマネージャーをやっていた女性も、出産後は後輩社員のアシスタントに異動させられていて驚いたものです。
この会社ではキャリアを積めないと思ったので転職をずっと考えていましたが、35歳を過ぎて年齢的にもそろそろ子供が欲しいタイミングだったので、今転職すべきかどうか迷っていました。
夫とも相談していろいろ考えた結果、絶対に子供が欲しかったので、妊活・妊娠・出産・育休復帰までは今の会社で頑張ることに。とにかく今の会社で育休を取るまでは頑張ろうという思いで、なんとかやってきました。
2回の妊娠初期流産の後、37歳で無事に出産して育休に。育休中から転職活動の情報収集を開始しました。
子供が生後4ヶ月のときに育休を切り上げて復帰し、育休復帰の半年後に転職をしました。赤ちゃんを育児しながらの転職活動はなかなか大変でしたが、無事に時短勤務の正社員で転職ができてよかったです。
もし出産前に転職していたら、転職してすぐに妊娠するわけにはいかないので、妊娠のタイミングを逃してどんどん年齢を重ねていたかもしれません。すぐにでも転職したい気持ちをおさえて、まずは出産を優先してよかったなと私は思っています。
まとめ
子供と転職、どちらを優先するかという問いに「正解」はありません。しかし、今働いている会社や自分の状況次第では、どちらを優先した方がよいか総合的に判断することは可能です。どちらの場合でも、転職するときは転職エージェントのキャリアアドバイザーを頼るなど工夫し、理想的な会社を探せるよう準備しておきましょう。
リアルミーキャリアでは、働き方を優先して転職したい方を支援しています。時短正社員転職やワーママ転職に強みがあるので、子育て前提で転職するときにもぜひご活用ください。


